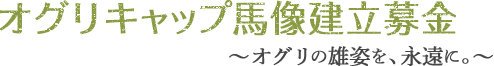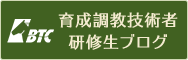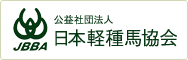軍土門隼夫(ぐんどもん・はやお)
1968年生まれ、神奈川県出身。早稲田大学文学部中退。競馬雑誌編集者を経てフリーのライターに。現在は『優駿』などに寄稿。
僕がきちんとした形で競馬を見始めたのは20歳を過ぎたばかりの頃で、ちょうどオグリキャップが4歳(当時の表記では5歳)秋にオールカマーで復帰する直前くらいのことだった。タマモクロスはもういなかったけど、その時点ですでにその名前と強さはよく理解できていたから、たぶん競馬初心者の例に漏れず、ものすごい集中力で勉強していたのだろう。それでも、たとえばウィナーズサークルが京都新聞杯で4着に負けたことは僕にとって完全に理解不可能な出来事だったし、毎日王冠でイナリワンがメジロアルダンより人気がないことをどうして誰もおかしいと思わないのか、謎で仕方がなかった。
要するに、オグリキャップを知った頃、僕は完全なる初心者だった。
その頃に競馬を始めた人がものすごく多かったと知ったのは、じつはちょっとあとになってからだった。実際には僕もいわゆる「競馬ブーム」に乗って始めた形なのだが、自分ではそういう意識はまったくなかったのだ。
親兄弟や友達など、周囲には競馬好きがまったくいなかった。僕の周りでは、競馬は別に「ブーム」でもなんでもなくて、競馬に関する情報は、完全に一人で、外部から得ていた。バブリーな時代のリズムにうまく乗れず、バンド仲間と古くさい音楽をやったり、一人で本を読んだり小説を書いたりすることを楽しいと思っているような、ドロップアウト寸前のさえない大学生が自然に興味を持つようになるほど競馬は「ブーム」だったのだと今ではわかるが、当時は、そこは自分自身で辿り着いた場所だと思っていた。
そんな僕のホームグラウンドは、WINS横浜だった。横浜市の北部に住んでいた僕は、中学生の頃に京浜急行を使って通学していたこともあって、横浜方面はずっと遊び場だった。だからまずそこに行ってみようと考えたのは自然な流れだったと思う。
競馬場に行くようになるのは、その後、大学を中退して逃げるように家を出て一人暮らしをするようになってからだった。そこで僕はやっと「競馬友達」を見つけたのだ。それまでの数年、僕はずっと一人でWINS横浜に通い続けていた。
当時は他に用事がない限り、WINSへは朝から行っていた。まだ人もまばらなフロアで、モニターを見上げて第1レースのアラブの未勝利戦のオッズを確認していたことは、まるで昨日のことのように思い出せる。
メインレースの頃には、いつもけっこうな混雑になった。階段も、裏手の駐輪場も人がいっぱいで、どこもタバコの煙が立ちこめていた。現在はA館とB館があるが、当時は建物も1つしかなくて、とにかくやたらと混んだ。
僕は朝から最終レースまでそこにいて、馬券を買って、当たったり外れたりしているというのに、来てから帰るまで一言も口をきかなかった。話す相手がいないのだからしょうがないし、それに、今でもそんな傾向はあると思うけど、たぶん競馬場よりもWINSの方が一人で来ているファンが多くて、黙って馬券を買い、黙ってモニターでレースを観るというのは、べつに不自然でもなんでもない行為だった。
そんなわけで僕には、オグリキャップについて誰かと語り合った記憶がまったくない。
いや記憶だけじゃなくて、本当になかった。友達とは、音楽のことや文学のことや人生のことや恋愛のことなど、たくさんのことを真剣に語り合ったが、オグリキャップについては、誰とも話をしなかった。そんな必要もなかった。僕にとって競馬とは一人で立ち向かっていくべき「何か」で、オグリキャップはその世界の親玉だったからだ。
その「何か」の正体をうまく言い表すことは、現在でもまだできない。
それは読み、理解し、把握し、そして未来を見通すことに全精力を傾けるだけの価値のあるものだった。
「個人」と「世界」の関係にも似たその戦いは、本質的に一人で遂行すべきものだと思われた。その、自分よりはるかに大きな「何か」を相手にしている時だけ、当時の僕は戦っているというリアルな実感を得ることができた。
そしてオグリキャップこそ、読み、理解し、把握し、そして未来を見通したくてたまらない対象の、その最たるものだった。
オグリキャップの引退レースとなった有馬記念の日、WINS横浜は未曾有の大混雑となっていた。いや、大レースの日はいつも、今では考えられないくらいの人が詰めかけたが、その日は特にひどかったと思う。
馬券売り場の窓口から続く行列は、階段を降り、外へと伸びて、建物の周囲を取り巻いていた。そこへ向かって、さらに桜木町や日ノ出町の駅から続々と人の群れが押し寄せるその光景は、ちょっと常軌を逸していた。
レースの1時間くらい前にはもう、係員だったか警察だったかが、その駅からやって来る人たちに対して拡声器で「今から来ても買えません!」と怒鳴っていた。嘘みたいだが本当の話だ。
今でも僕にとっては、オグリキャップという名前はWINS横浜のあの光景の記憶とまっすぐに結びついている。その姿は、狭いフロアにすし詰めになって立ち、みんなで見上げている小さなモニターの中のものであり続けている。そこで僕はオグリキャップと、いやもっと大きな「何か」と戦っていたのだ。
現在、僕は末席のさらに隅っこのような場所だけど、競馬に関する文章を書くことを仕事にするようになった。競馬場に行けば必ず知っている人がいて、挨拶を交わしたり、パドックの感想を述べ合ったり、予想を開陳したり、いっしょにレースを観たりもできるようになった。そんな僕の姿は、オグリキャップの眼にはいったいどう映っているのだろうか。
お前、まだちゃんと戦っているか?
時々、どこからかそう問いかける声が聞こえてくるような気がする。