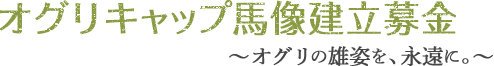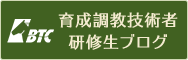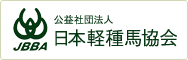島田明宏(しまだ・あきひろ)
1964(昭和39)年11月2日、北海道札幌市生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科中退。早大在学中より放送作家、フリーライターとして執筆活動にとりかかる。90年夏から武豊騎手の米国遠征に同行し、「Number」「別冊宝島」「週刊文春」などで競馬の原稿を書くようになる。並行して、男性誌や自動車専門誌でモータースポーツの取材記事、「週刊朝日」「DIME」「プレジデント」「週刊ポスト」などで時事ノンフィクション、インタビュー記事、書評などを執筆。訳書に『きらめく瞳に会った』(93年、山海堂)、著書に『「武豊」の瞬間』(99年、集英社文庫)、『ありがとう、ディープインパクト』(07年、廣済堂出版)、『伝説の名ジョッキー』(08年、ゴマブックス)、『ウオッカ物語』(10年、廣済堂出版)など。現在、「優駿」や、携帯サイト「競馬総合チャンネル」などに寄稿するほか、「週刊競馬ブック」でエッセイ「競馬ことのは」を隔週で、競馬月刊誌「UMAJIN」でコラム「島田明宏のフォーカス」などを連載中。09年、競馬小説「下総御料牧場の春」で第26回さきがけ文学賞選奨を受賞。
オグリキャップが旧4歳時、12戦10勝2着2回という戦績を引っさげて中央入りした88年春、私は別の芦毛馬に夢中になっていた。のちにオグリと熾烈な「芦毛対決」を繰りひろげるタマモクロスである。
タマモは、前年12月の鳴尾記念でも、この年の金杯でも、直線で前が詰まると態勢を立て直して伸び、また詰まっても伸び…と、普通なら絶対に差し届かない不利をモノともせず重賞を連勝した。つづく阪神大賞典こそ同着での優勝だったが、天皇賞・春を圧勝し、次走の宝塚記念でマイル王・ニッポーテイオーを下した時点で、日本のサラブレッド界の頂点に立った。と、私は思い込んでいた。
ところが、である。
タマモが勝った宝塚記念の前週のNZT4歳Sで中央重賞4連勝目を挙げたオグリの、まあ強いこと。古馬との初対決となった高松宮杯(当時は2000mのGⅡ)も、つづく毎日王冠も単勝1倍台の圧倒的支持に応えて楽勝。クラシック登録されていなかったため、菊花賞ではなく、天皇賞・秋、ジャパンC、有馬記念というタマモと同じ路線を進むことになった。
その年、私は24歳になろうとしていた。何が言いたいかというと、若かった、ということだ。普通、若者は自然と新興勢力の側につくものだが、私は、オグリより1歳上の「タマモ派」でありつづけた。
オグリは激戦を激戦と感じない「スーパー体力」の持ち主で、夏を越してひと回り大きくなった馬体は、秋初戦の毎日王冠を使われてさらに充実していた。それに対し、タマモは、ひとつ競馬を使うたびにガクッと疲れが出てカイ食いが落ち、馬体を維持するのに苦労する馬だった。
私は、ゴレンジャーでは脇役のアオレンジャー、仮面ライダーシリーズでは人間っぽさが残るライダーマン、キカイダーなら強い01(ゼロワン)より初代キカイダーに肩入れするタイプだった。なんでもかんでも判官贔屓というわけではないが、どこか脆さのあるヒーローになぜか惹かれてしまうのだ。
そんなわけで、私にとってのオグリは、アカレンジャーであり、仮面ライダーV3であり、キカイダー01でもあるという、肩入れする必要のまったくない、強すぎる主役であり、正統派すぎるアイドルであった。地方競馬の笠松出身ということも、私自身、地方都市の札幌出身であることをハンデに思ったことがないせいか、シンパシーを感じる材料にはならなかった。
そのオグリとタマモによる「芦毛対決」の第1戦は同年、88年秋の天皇賞だった。それまでオグリは地方時代から数えて14連勝(うち中央の重賞6連勝)。タマモは7連勝(うちGⅠ2連勝を含む重賞5連勝)。どちらかの戦績に傷がつくのがもったいないとさえ思われたこの戦いを制したのは、タマモだった。
タマモ派の私としては確かに嬉しかったのだが、オグリと差し脚比べをすると思っていたところ、意表をつく感じの先行策をとって勝ったせいか、感じたのは、いささか微妙な喜びだった。芦毛対決第2戦のジャパンCでは、タマモ2着、オグリ3着と、またも微妙な結果に終わった。そして、これを最後に引退するとタマモ陣営が宣言していた、芦毛対決最終戦の有馬記念では、オグリが、「勝ち逃げはさせない」という陣営の言葉どおり、タマモを2着に封じて優勝。タマモは、カイ食いが落ちて調教をセーブせざるを得ず、中山でスクーリングを兼ねた1週前追い切りをしても元気一杯だったオグリに、レース前から勝てそうな雰囲気がなかった。
まさに完敗。悔しいというより、素直にオグリに脱帽、という気分だった。
翌89年、オグリは脚部不安のため春は休養したが、秋にはタマモの主戦だった南井克巳を鞍上に迎え、毎日王冠でイナリワンとの叩き合いを鼻差で制し、強いオグリが健在であることをアピールした。天皇賞・秋では武豊・スーパークリークに敗れるも、マイルCSで武のバンブーメモリーを鼻差かわし、連闘で臨んだジャパンCでは世界レコードの2着に激走するなど、多くの人々を感動させた。いつの間にか、私も、そんなオグリの走りに熱狂していた。
巨額のトレードマネーを回収するため過酷なローテーションを強いられているのではないか…といった憶測が飛び交うなか、人間の思惑をよそに、オグリは、ひたすら一生懸命ゴールを目指しつづけた。
「どんな不利があっても、最後まで諦めなければ道はひらける」と教えてくれたのはタマモクロスだった。オグリキャップは、その教えを実践するための「燃料」に相当する「勇気」を、私に与えてくれた。もっと身勝手な言い方をすると、オグリは、私にとって最強馬だったタマモを負かした馬の義務として、タマモ引退後も強い姿を必死になって見せつづけてくれたのかもしれないと、私は一方的に思っている。
ともあれ、大学を中退して文筆一本の道を歩みはじめたばかりだった私は、タマモとオグリに出会ったことで、競馬の魅力をペンで伝えていきたい――と、強く思うようになった。
あれから20余年。今思うと、オグリやタマモをはじめ、ホクトヘリオス、ハクタイセイ、メジロマックイーンなど、強く、個性的な芦毛馬とともに多感な20代を過ごした自分たちは「芦毛世代」と言っていいような気が、急にしてきた。
芦毛世代のひとりとして、これからも天国のオグリに勇気を分けてもらい、力一杯、文章を書きつづけたいと思う。