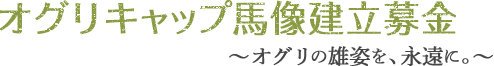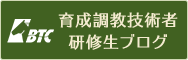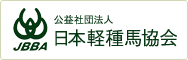福原直英(ふくはら・なおひで)
東京都出身。フジテレビアナウンサー。日曜日のフジテレビ競馬中継『みんなのKEIBA』の番組MCを務める。また、CS放送の『武豊TV!II』のナビゲターを務める他、週刊GALLOPにて『福原直英アナの招福馬来』を連載。フジテレビアナウンサーページ『アナマガ』にて”新・馬、そしてそれ以外も”を好評連載中。
僕らが初めて見たオグリキャップは、黒い馬だった。
1988年、ニュージーランドトロフィー4歳ステークス。
この日僕は、高校の同級生に誘われて東京競馬場に行った。
もちろん目当てはこの馬、とのことだった。
「とのこと」?他人事のようだがその通りなのだ。
僕はオグリキャップを、ほとんど知らなかった。
でもその友人は、よく知っていた。
笠松の怪物、中央入り緒戦が重賞勝ち、そして関西で連勝中…。
彼は決して、笠松に行ったことがあるわけでもない。関西人でもない。そして(これは僕にも共通することだが)、周りの家族親類、みな競馬をやらない。
ではなぜ、この時点のオグリキャップが、お目当てになるのか。
それは彼が、競馬四季報を欠かさず買い求め、それを「ア」から順番に読んでいくような男だったからだ。
「オ」グリキャップは、そんな彼の関心をひくのに十分すぎた。そしてついに、家から見に行ける場所に、オグリキャップはやってきてくれたのだ。
はたしてどんなレースをするのか?決して見栄えがいいわけではない。自分にはっきりわかるくらいのオーラがあったとしたなら、もっと別の舞台が用意されていただろう。ハナから中央競馬でデビューしていたライバルたちにも、オグリと同じかそれ以上の期待を抱いていた人がいたのは事実である。
当時の僕らは、パドックを見て、返し馬を見て、それからゴール板まっ正面の柵に陣取るのが常だった。馬を見たいから馬の見える場所を移動し、どれが勝ったかをこの目で見たかったから、その場所に向かう。ハイセイコー以来の競馬ブームを演出するオグリキャップ、その兆しはまだ、ほんの少ししか見られなかった。だから、そんな僕らの導線は難なく手に入るものだった。
レース直前、僕らは思いがけないものを目撃した。当時欠かさず見ていたといっていいUHF局の競馬中継、そのアシスタント嬢が僕らと同じ柵に並んでレースを待っているではないか。「テレビに出ている人だ!」すかさず友人が話しかける、でも二言目が続かない。青かった。今はこんな思いをしたくてもできなくなってしまっている身の上ではあるが、バブルに浮かれ始めていた当時でさえ、こんなこと=僕らの動きや彼女の観戦スタイル、ができる時代だったともいえる。
レースが始まった。言っておくが彼は強烈な逃げ馬でも、追い込み馬でもない。道中になにを感じたかなんてありゃしない。想像できることはひとつ、目の前でどんな勝ちっぷりを見せてくれるかだった。
確かに強かった。ライバルという言葉自体も霞んでしまうくらいの圧勝だった。条件戦ならまだしも、G2でこんなに他を引き離すとは…これは「競馬四季報」の通りだった、そう感じた。そして気づいたときにはもう、かのアシスタント嬢は姿を消していた。
それから僕らはオグリキャップとともに数年を過ごすことになる。
そのほとんどが、自分にとっては未知の、こんなものもあるんだという世界の話に思えたものだ。高松宮杯でランドヒリュウを負かしたとき。年上の馬にこうやって勝てるものなんだ、感心した。秋の毎日王冠。同世代が菊花賞路線に向かう中、今度はダービー馬シリウスシンボリも含めての古馬撃破。そして天皇賞。タマモクロスが立ちはだかるのか、それともオグリキャップはG1馬の称号を得るところまで一気に駆け上がるのか。あの初夏の陽気から半年、府中の森ははっきりとオグリキャップを怪物と意識しての客であふれていた。もう僕らにいつもの導線は許されなくなっていたのだ。
それでもなんとか確保したゴール前。黒から灰色へ、心身がまるで脱皮したかのようなオグリキャップと、一足先にオトナの馬になっているタマモクロス。先輩が2番手につける姿がターフビジョンに映ったのが見えた。「オグリは負ける」直感した。すでにG1を勝っているタマモクロスが自らの追い込み戦法を捨て、敵に脚を使わせながらの先行策…これでは勝てない、そう思ったのだ。
翌年の有馬記念、イナリワンとスーパークリークの争いに参加できなかった時も予感があった。いや、そのカンを言いたいのではない。生来のギャンブル音痴である自分は、滅多なことで勝負の行方を思い描けないのである。なのに、オグリキャップにはそれを感じた。なぜだろう?今に至るまで僕は、競走馬の擬人化が好きではない。だから彼ら彼女らの生の行方も、それほど考えない。でもオグリキャップは違ったのだ。決して意識的にではないのだけれど、実は僕が彼に、一方的に寄り添っていたのだと思う。彼がきっと、惹きつける力があったのでは…そうでないと説明がつかないのだ。当時の僕は、レーシングプログラムにパドックで見た感想をどの馬にも書き留めていた(とはいっても『太い』『イレ込んでいる』なんてありのままを書くことも少なくなかったが)。オグリキャップにはこう書き続けている。
「いつも通り」と。
そう、ラストランも中山に向かった。パドックでオグリキャップを見た。そしてこう記した「いつも通り」そのいつも、とは僕らが初めて生でオグリキャップを見た、あの日が基準になっている。あの時の強さのままでいるはず、いてほしい…ああやはり、僕らは彼に寄り添っていたのだ。そして僕の予想は外れた。最後まで彼が何者であるかわからないままに、彼を競馬場から見送ったのだった。
翌年、僕らは北海道へ向かった。レンタカー、オートバイ、自転車。あらゆる交通手段を使って、全国からオグリキャップ詣での夏だ。オグリキャップは確かにいた。しかし、誰からも離れた、放牧地の一番奥にいた。「オレの何がわかっているというんだい?」そう言われているような気がしてならなかった。あれほど嫌っていた擬人化をして、そうでもしないとあの、遠くに佇んだままのオグリキャップを「見たことにして」その場から去るきっかけをつかめなかったのだ。
その後、競馬を取材・放送する仕事につき、2000年のこと。同じ種馬場でオグリキャップと再会した。あの時が嘘のように、オグリキャップはスタッフに引かれゆっくりと僕のもとへ歩いてきた。好々爺然としたオグリキャップ。その姿を見て、あの黒い馬はダブらなかった。いや、人も馬も、それが生きることなのだ、と思った。
オグリが死んだって。
そう聞いて真っ先に浮かんだのは、この年のオグリキャップの姿である。
でも僕らは生きる。生きている限り何通りものオグリキャップを思い出す作業ができる。黒い馬、古馬を撃破した馬、そして負けを覚悟した馬。それぞれのオグリキャップを、それぞれの立場で。
ちなみに今、一緒にオグリキャップを見に行った「僕ら」のもう一人は、東京の会社を辞して競馬の世界で生きている。去年は凱旋門賞にも帯同した。彼の流転も含めて、今もオグリキャップと僕らは、色濃い競馬の記憶とも寄り添って、生きている。