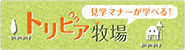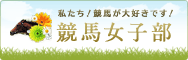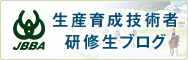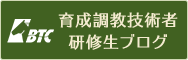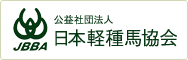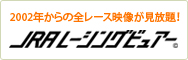軽種馬育成調教センターが育成調教技術者養成研修第43期生開講式を執り行う
4月22日、浦河町西舎にある公益財団法人軽種馬育成調教センター(草野広実理事長)は、浦河町西舎のうらかわ優駿ビレッジAERU(アエル)において、育成調教技術者養成研修の第43期生開講式を執り行った。
第43期生は、青森県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福井県、愛媛県、岡山県、宮崎県出身の18歳から25歳までの27人。競争倍率約3.5倍の応募者のなかから選考試験を経て合格した。
第43期生や草野広実理事長をはじめとした公益財団法人軽種馬育成調教センターの役職員が出席した開講式では、第43期生27人の氏名が読み上げられ草野広実理事長が入講を許可。続けて草野広実理事長は「みなさん、研修への入講、まことにおめでとうございます。みなさんは大勢の入講希望者のなかから、この研修への参加意欲が高いということを認められて、いま、ここに集まっています。これから一年間、研修修了を目指して、一生懸命がんばってください。この研修を修了した人たちの感想文を見ますと、いままで生きてきたなかで一番がんばった一年だった、一年前の自分と現在の自分を比較すると明らかに成長していることがわかる一年でした、というようなことが書かれています。みなさんも来年のいまごろは、そういう気持ちになっていることでしょう。さっそくみなさんに、心がけていただきたいことがあります。それはこの27名の仲間でよくコミュニケーションをとり、集団生活に慣れて、そして、いろいろな場面で設定される集合時刻に、絶対に遅刻しないということであります。馬は草食動物で、群れで行動する生き物ですから、育成牧場では毎朝複数の馬が連れ立って調教にいきます。そうするためには朝の集合時刻に遅れない、そして、今日一日の仕事のスケジュール、それぞれの馬の状態の確認、そういったことをしてからの仕事になります。育成牧場で働くというのはそういうことからはじまります。そういうことを心がけて過ごしてください。
次に乗馬訓練ですが、年間で400鞍くらいあります。乗馬経験のない、ほとんど馬に乗ったことがない、そういった人でも、来年のいまごろには、JRAの育成馬に乗って、1ハロン13秒前後くらいで走れるような技術がついているはずです。実際、4月15日のJRA育成馬展示会がありました。当日、馬場が良かったこともありますが、最後の1ハロンを12秒を切るタイムで走れている研修生もいました。そういうふうになれるはずですが、みなさんが漫然と乗馬訓練の授業に参加しているだけでは自然と乗馬がうまくなることはありません。教官から細かく指示があります。できるまで繰り返し練習して、わからないことは何度でも教官にアドバイスを求めてください。
5月からは乗馬に必要な筋肉や体幹を鍛えるトレーニングの授業もはじまります。インストラクターは個別のメニューをつくってくれます。体が疲れていても自主的にトレーニングしてください。乗馬シミュレーターにも毎日乗ってください。この毎日の努力をやった人とさぼった人との差は、秋ごろから明確に出てきます。一日一日を真剣に向き合っていただきたいとおもいます。努力をすれば技術は身につきます。そして、この研修をやり遂げた先には、それぞれの就業先の牧場で、必ずやリーダーシップを取れる人材になり、ゆくゆくは自分で育成牧場を経営、競馬場のスタッフから調教師を目指す、というような可能性も広がります。そういう期待と心構えを皆さんにお伝えします」と式辞を述べた。
開講式後はJRAからの出向した2人を含めた7人の教官を紹介。27人の第43期生も自己紹介と研修への意気込みを語った。
育成調教技術者養成研修は、競馬の安定的発展のための軽種馬生産基盤の強化と軽種馬の資質向上に向けて、将来軽種馬生産地において技術的中核となるべき者に馬に関する体系的な技術・知識を習得させることを目的としたもので1992年に開講。研修期間は1年で、前半の6か月間で軽種馬の育成調教技術者として就労するための基礎的な知識・技術の習得を目標とし、後半の6か月間では前半の6か月間で学んだ知識・技術をさらに深めるとともに、若馬の馴致・初期調教を含めより実践的な技術の習得を目標としている。これまでに送り出した研修修了生は637人。日本の軽種馬育成を支える人材として活躍している。