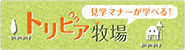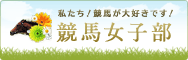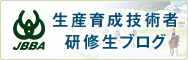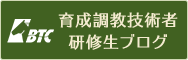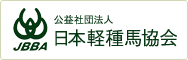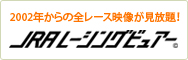日本軽種馬協会静内種馬場で2021年(第43期)生産育成技術者研修開講式
4月2日、公益社団法人日本軽種馬協会(河野洋平会長理事)は、新ひだか町静内田原にある静内種馬場研修所において、2021年度(第43期)生産育成技術者研修開講式を執り行った。
第43期生は、北海道、青森県、神奈川県、東京都、静岡県、富山県、滋賀県、和歌山県、奈良県、島根県出身の18歳から22歳の14人(男性9人、女性5人)。オンラインによる選考試験を経て入構した。
開講式は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地元行政や軽種馬関係の来賓、研修生の家族などの出席を取りやめて挙行。研修生紹介後に遊佐繁基場長が「2021年度生産育成技術者研修生14名の入講を許可いたします」と入構を許可した。
本部から出席した山岸直樹事務局長は「本日、入所された14名の研修生の皆さんには、心からお祝い申し上げます。例年であれば、本席には、地元行政や軽種馬生産関係者のご来賓、そして、皆様のご家族のご臨席を賜り、門出を祝っていただくところでございますが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に終息が見えないため、本日は、関係各位のご出席をご遠慮いただき挙行することとなりました。皆さんには大変申し訳なく思っておりますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
さて、昨年の競馬開催を振り返ってみますと新型コロナウイルス感染拡大防止策に最善を尽くし、史上初の無観客競馬が開催された中、世代を超えた三冠馬による白熱したレースが実現し、大いに競馬を盛り上げてくれることとなりました。日本の競馬をよりいっそう魅力的なものにし、この産業をさらに盛り立てていくためには、今後も強い競走馬を生産育成することが重要な課題となっております。そのためには、何よりも生産と育成の分野における優れた技術者の養成が不可欠です。
本協会では、わが国の競馬をいっそう発展させ、また、生産界の期待に応えうる生産育成技術者を養成するため、平成2年秋から本研修を開催しております。今年ですでに30年の歴史を有し、これまでに464人にのぼる修了生を軽種馬生産界に送り出してきました。本研修事業に対する競馬サークルの期待は大きく、歴代の修了生もこの期待に応えるべく、それぞれの職場で大いに活躍されております。
皆さんが本日から受ける研修の内容は多岐にわたっており、騎乗技術、馬の飼養管理や繁殖に関する幅広い知識等に加え、およそ牧場で必要となる作業全般について体得していただくこととなります。
研修中はどうか健康に留意され、ホースマンとしての研鑚に努め、1年後には1人も欠けることなく、晴れやかな笑顔で修了式を迎えられることを切に願ってやみません。そして、皆様には、これからの生産界に、新たな活力をもたらす原動力に、ぜひなっていただきたいと思っております」と河野会長理事の式辞を代読した。
続いて第43期生を代表して北海道出身の上水隆生さんが研修生宣誓。「わたしたち第43期生産育成技術者研修生は、軽種馬生産界の期待に応えるよう、地域に根差した軽種馬産業の担い手として一流のホースマンを目指し、常に向上心と探求心を持ち、知識、技術を高めることを誓います」と力強く宣誓した。
開講式後は研修所の食堂に会場を移し昼食会を開催。遊佐場長は「皆さん、北海道にようこそいらっしゃいました。これから1年間、いろいろ学んでいきます。最初はできないのが当たり前です。心配しないでください。先日、第42期生が研修を修了して旅立ちましたが、入ったときはできませんでしたが出るときには立派になってました。1年はあっという間です。1日1日を大切にして一生懸命学んでください。教官がやさしく教えてくれます。時には大きな声を出すときもあります。それは皆さんの安全のことを思ってのことです。決して叱ってるわけではありません。皆さんのことを思って指導しますので理解して研修に励んでください」と歓迎した。
第43期生の研修プログラムは、繁殖学、基本馬術、馬学、情報処理関連、土壌草地管理、蹄管理、馬の栄養飼料、馬の疾病などの講義、馬への接近、曳き馬、手入れ、部班運動、発進、停止、回転、走路騎乗、ロンジング、ドライビング、ハミ受け、低障害飛越などの騎乗、堆肥造成、厩舎清掃、草刈り、牧草収穫、環境整備などの作業、JRA育成馬展示会見学、せり見学、JRA繁殖馬・当歳馬管理実習、競馬場見学、民間育成牧場実習などの実習・見学など。研修用乗馬は23頭で、その中には2013年の朝日チャレンジC(G3)優勝馬アルキメデスや2013年のシリウスS(G3)優勝馬ケイアイレオーネもいる。