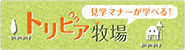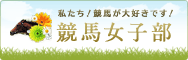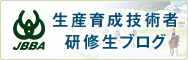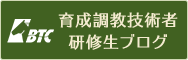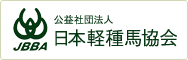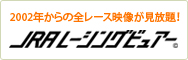日本軽種馬協会2016年(第38期)生産育成技術者研修が開講
4月5日、日本軽種馬協会は2016年(第38期)生産育成技術者研修の開講式を、新ひだか町静内田原の静内種馬場研修所で行った。
この研修は、わが国の競馬をいっそう発展させ、また、生産界の期待に応えうる生産育成技術者を養成するため、JRA日本中央競馬会の助成を得て、平成2年秋から開催。今年ですでに26年の歴史を有し、これまでに416名にのぼる修了生を軽種馬生産育成界に送り出している。
第38期生は、約30名の志願者の中から、筆記試験(作文)、面接試験、口答試問、運動適性検査といった選考試験を経て選ばれた18歳から29歳の12名(男性9名、女性3名)。北は北海道、南は九州の佐賀県と全国各地から集まった。12名には道内の牧場後継者や父がJRA調教師、兄がJBBA研修修了生もいる。高校を卒業したばかりの若者が多く、約8割の研修生はBOKUJOBフェアや体験入学会の体験者だという。
開講式では、石田牧彦研修課長が研修生の名を1人ずつ読み上げ紹介したあと、中西信吾場長が入講を許可。本部から駆けつけた柴田晃一事務局長は「本日、入所された12名の研修生の皆様には心からお祝い申し上げます。わが国は平成19年に、国際的に認められたパートⅠの競馬国となり、名実ともに競馬先進国の仲間入りを果たしました。そして、昨年12月の香港の国際レースで日本馬が2勝をあげるなど、日本馬は近年、その実力を世界の舞台で示しております。そのようななか、わが国の競馬産業、そして、生産界を取り巻く経済状況は、若干明るい兆しも見えていますが、日本の競馬をよりいっそう魅力的なものとし、この産業を盛り立てていくには強い競走馬を生産育成することがますます重要な課題となります。そしてそのためには何よりも、生産と育成の分野における優れた技術者の養成は不可欠であります。本研修事業に対する競馬サークルの期待は大きく、歴代の修了生もその期待に応えるべく、それぞれの職場で大いに活躍されております。皆様が本日から受ける研修の内容は多岐に渡っており、騎乗技術、馬の飼養管理や繁殖に関する幅広い知識等に加え、およそ牧場で必要となる作業全般について体得していただくことになります。研修中はどうか健康に留意され、ホースマンとしての研鑚に努め、1年後には1人も欠けることなく晴れやかな笑顔で修了式を迎えられることを切に願ってやみません。そして、皆様にはこれからの生産界に新たな活力をもたらす原動力にぜひなっていただきたいと思います」と河野洋平会長理事の式辞を代読した。
続いて来賓として出席した日高振興局の金崎伸幸副局長が「優駿のふるさと日高にお越しいただき、心より歓迎申し上げます。皆様は、道内をはじめ南は九州まで、全国各地から馬の生産育成技術者を目指し、集まってこられたと聞いております。中にははじめて馬に触れるという方もいらっしゃると思いますが、今日からは目標の実現に向け、お互いに協力し支え合い、講習やトレーニングに励んでいただきたいと思います。日高管内で生産された競走馬は、JRAやホッカイドウ競馬など、全国の競馬場で活躍しておりますが、とくに北海道が主催しているホッカイドウ競馬は、日高で生産された2歳馬が初めて出走する、馬産地ならではのものでございます。また、最近では海外のレースや国内のG1レースにおいて、日高産の多くの馬が優勝しており、その影には一流馬を育成調教する人の存在が欠かせないものとなっております。日高管内はこれから春を迎えます。5月には、この研修施設の近くを走る二十間道路では、日本一の桜並木が見られます。また、日高管内の海の幸、山の幸が豊富でございます。これからの時期はウニやアスパラ、イチゴなどの食材が旬を迎えますので、休日にはぜひ楽しんでいただきたいと思います。『馬に人は学び、人は駿馬をつくる』といいます。1年後には、皆様も国内で、世界に認められる競走馬を育てる原動力として、そして、男性も女性も、日高が誇るホースマンとして、成長されることを心より期待しております。研修中は怪我などなさらず、来年3月の修了式を皆様で迎えていただくと共に、有意義で充実した1年間になるよう祈念いたします」と祝辞。
JRA日高育成牧場の上野儀治副場長は「若い皆様が生産育成を志してこの研修に入られたことに対し、競馬関係者のひとりとして非常にうれしく思っております。日本の馬は昨年の香港や先日のドバイで勝ったように、世界でも1、2のレベルにあると思いますが、馬を扱う人間のほうは、まだまだ世界トップとはいえません。ここで勉強したことを礎にして、馬も人も世界一だといえるような人材になってほしいと思います。愛する馬と関わる人たちを幸せにできるようなホースマンになってください。皆様には孔子の『これを知る者はこれを好む者に如かず、これを好む者はこれを楽しむ者に如かず』という言葉をアドバイスとして贈ります」、日高軽種馬農業協同組合の藤原俊哉副組合長理事は「皆様は本日から軽種馬の生産育成の技術を身につけるため、日々の努力をされることと思います。私どもはその現場で、生産から育成まで一貫して取り組んでいますが、馬は言葉をしゃべらないので、子育てより難しいことと感じています。馬は24時間心配です。大変なこと、かわいそうなこと、たくさんあります。ですから自分が携わった馬が競馬場でデビューし、優勝したときの喜び、経験は、なにごとにも代えがたい達成感が得らます。一年間頑張って全員で修了式を迎えられることを祈っています」と、それぞれ激励の言葉を送った。
最後は第38期生を代表して京都府出身の松崎典子さんが宣誓。「私たち第38期研修生は、一流のホースマンになるべく、夢と目標に向かって、全員でこの1年間の研修に取り組んでいくことをここに誓います」と目を輝かせた。
研修では、馬の種類、馬体の名称、馬の個体識別、護蹄、馬の運動といった「馬学」、牝馬の生殖器、発情周期、分娩管理、当歳馬の疾病といった「繁殖学」、乗馬・下馬、馬上体操、部班運動、馬体の動きといった「基本馬術」、堆肥造成、厩舎清掃、草地管理、草刈り、農業機械取り扱い、環境整備といった「作業」、JRA育成馬展示会見学、JRA繁殖牝馬・当歳馬管理実習、せり見学、せり馴致実習、中央競馬見学、JBBA種馬場実習、民間育成牧場実習といった「実習・見学」、筋トレ、ストレッチ講習、シベチャリ駅伝参加、球技大会、馬術大会、レクリエーションなどがカリキュラムされている。
研修用乗馬は21頭。2000年のマーチステークス(G3)優勝馬タマモストロング、2013年の朝日チャレンジカップ(G3)優勝馬アルキメデス、2010年のエルムステークス(G3)優勝馬クリールパッションなどの重賞勝ち馬も、生きた教材として一流競走馬の乗り味を伝える。