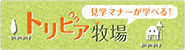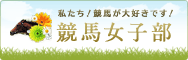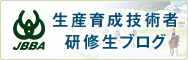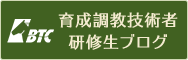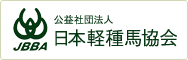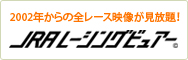「強い馬づくりのための生産育成技術講座2011」が行われる
11月15夜、日高町の門別総合町民センターにおいて、JRA日高育成牧場主催による「強い馬づくりのための生産育成技術講座2011」が行なわれた。
この講座は競走馬の資質向上や生産育成関係者への情報・技術普及を目的としたもの。日高軽種馬生産振興会青年部連合会が共催し、HBA日高軽種馬農業協同組合が後援している。会場は用意した席が足りなくなるほどの軽種馬関係者が集まり、熱気を帯びた講座となった。
開会に先立ち、オブザーバーとして出席した門別軽種馬生産振興会青年部の若林部長が挨拶。「本日は3名の講師の方をお招きしております。これを機に早期発見、早期治療に役立てていきましょう」と呼びかけた。
公演内容は「子馬の肢軸異常・クラブフット調査」(講師:JRA日高育成牧場生産育成研究室佐藤文夫氏)、「馬の皮膚病とその対策」(講師:JRA日高育成牧場業務課診療防疫係長遠藤祥郎氏)、「繁殖シーズン前の飼養管理」(講師:日高軽種馬農業協同組合浦河診療所敷地光盛氏)の3つ。JRA日高育成牧場生産対策室の南保泰雄氏が司会進行を務めた。
佐藤氏は肢軸の見方、子馬における肢勢異常、成長に伴う肢勢の変化、クラブフットの発症と対処法について説明。肢軸異常には先天的なものと後天的なものがあり、先天的なものは「遺伝によるもの、胎内での姿勢によるものがある」とし、後天的要因は成長に伴う腱靭帯の拘縮やアンバランスがあり、「早めの発見が大事と訴えた。また、成長に伴う肢勢は3か月から4か月齢に多く見られることから、この時期の注意を促した。最後にクラブフットの対処として「蹄に触れる、よく観察する、蹄洗」といった日常の蹄管理の重要性を説き、「異常を見つけたときは生産者、獣医師、装蹄師で良く話し合って最善の方法をみつけてほしい」と結んだ。
遠藤氏は皮膚病の種類、治療法などを講演。皮膚病には感染性のものと非感染性のものがあるとし、感染性で範囲が狭いものは抗生物質、抗真菌薬を用い、範囲が広いものは消毒薬や抗ヒスタミン剤、ステロイドなどを投与するとした。皮膚病を予防するには「疲労・ストレスを蓄積させない。手入れをし汚れを取る」と論じた。
敷地氏は妊娠後期の栄養管理、BCS管理(ボディコンディションスコア)、歯の管理を主に紹介。妊娠後期には「微量元素などのミネラル給与が重要」と話した。BCSは妊娠馬については5~6が適切とし、馬の歯は成馬になっても伸び続けるため、「年に1度は検査を」と提案した。さらに妊娠5週~分娩までに胎子喪失率は8.7%という数字を示し、「妊娠後期にも定期診断しましょう」とモニタリングを呼びかけた。
講演後、主催者を代表し平賀敦JRA日高育成牧場副場長が結びの挨拶。「このような集まりは素晴らしいことなので、今後も続けていきたい。皆さんからの意見を参考に来年のテーマを決めていきたいと思っています。これからも皆さんとともに日高の生産育成技術を高めていけたら良いと考えています。お忙しい中、夜遅くまでありがとうございました」と礼を述べた。
なお、同講座は翌16日にも浦河町の堺町基幹集落センターで行われた。