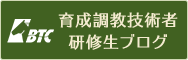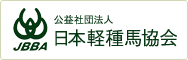ライターの馬産地紀行 Vol.15~山田 康文
Vol.15 山田康文~初めての馬産地の想い出
おぼろげな記憶をたどってみる。初めて馬産地北海道を訪ねたのは、1983年。今から約四半世紀前のことだ。当時、大学生だった私は、アルバイトをして貯めたお金で買ったカメラを片手に千歳空港に降り立った。たしか、生まれてはじめての一人旅だったような気がする。
右も、左も分からない。千歳空港から苫小牧駅へ。たぶん、今よりは運行本数も多かったはずだが、苫小牧で2時間くらい待たされたような気がする。予定も何にもなかった。まだ「ふるさと案内所」もない時代。どうやって調べたのか思い出せないのだが、会いたい馬がいる牧場、種馬場の住所だけをメモしたノートを片手に日高本線に乗り込んだ。
最初に降りたのが「日高富川」駅。季節は秋だった。時間は、午後3時を少しまわったくらいだったような気がする。汽車から降りて、駅員さんに泊まれるところを訪ねた。それすらも決めてない旅だった。親切な駅長さんが、近くのペンションを紹介してくれた。しかし、どうやら宿と連絡がつかない。まだ携帯電話なんてない時代だ。
「そういえば(ペンションの)奥さんが(たぶん)生協で買い物してたの見たぞ。今日はカレーライスだと思う」という笑い声が駅舎に響いた。
「馬、見に来たんだべ。見ておいで。その間に連絡とっておくから」という言葉を頼りに、徒歩で目的地に向かった。
最初にたどり着いたのは日高軽種馬農協門別種馬場。大好きだったホウヨウボーイが、たった1年だけ過ごした種馬場だ。そのとき、すでにホウヨウボーイはいなかったが、グリーングラスがいた。現役時代の記憶はほとんどないが、美しい響きのある名前は印象的だ。
「あの馬は、人がくると尻をむけるから写真を撮るのは難しいよ」とスタッフに言われ、カメラを片手に放牧地に。
何のことはない。見知らぬ人間に気がついたグリーングラスは、トコトコと近くにやってきた。 初めて間近にみる馬の大きさと、黒光りする迫力ある馬体に圧倒されながらも、夢中でシャッターを切った。
満足そうにする私に「ほかの馬はよいのかい?」と作業を終えたスタッフが声をかけてきた。「えっと、あとは何がいるんでしたっけ」と私。
それまで、好意に満ちていたスタッフの凍った表情は今でも忘れられない。「タネウマ持ちは、業界の花形」という言葉は、相当あとで知ったフレーズだが、競走馬と、それに携わる人たちのプライドを思い知らされた瞬間だった。
その日からスタートした約1週間の馬産地紀行は、新冠、静内、三石を経て、浦河町まで。
シンザンとタケホープ、そしてトウショウボーイが最後の被写体だったと記憶しているが、36枚撮りフィルム20本をすべて撮りきって終えた。まだ車の免許も持たないときだったので、移動は徒歩、それにタクシーとバスを使った。そして、多くの牧場の人たちの好意に甘えさせてもらった。
今考えれば恐ろしいことだが、すべての訪問がアポなしだった。歩いていたら陽がすっかりと落ち、真っ暗になった牧場の門を叩いたこともある。まるで「田舎に泊まろう」の世界だ。
その牧場では本当に「泊まっていけ」といわれて一宿二飯の恩義を受けた。朝食でいただいたおにぎりと味噌汁の味はいまでも忘れることはできない。
すっかり日高の虜になった「東京から、馬の写真を撮りにきた変わり者」はそれから4年間、同じような時期に馬産地日高をたずね、そして今ではほぼ毎週のように日高のどこかにいる。
風景は、すっかり変わってしまったが、今でも変わらない空気と時間が流れている。そんな日高が大好きだ。
おぼろげな記憶をたどってみる。初めて馬産地北海道を訪ねたのは、1983年。今から約四半世紀前のことだ。当時、大学生だった私は、アルバイトをして貯めたお金で買ったカメラを片手に千歳空港に降り立った。たしか、生まれてはじめての一人旅だったような気がする。
右も、左も分からない。千歳空港から苫小牧駅へ。たぶん、今よりは運行本数も多かったはずだが、苫小牧で2時間くらい待たされたような気がする。予定も何にもなかった。まだ「ふるさと案内所」もない時代。どうやって調べたのか思い出せないのだが、会いたい馬がいる牧場、種馬場の住所だけをメモしたノートを片手に日高本線に乗り込んだ。
最初に降りたのが「日高富川」駅。季節は秋だった。時間は、午後3時を少しまわったくらいだったような気がする。汽車から降りて、駅員さんに泊まれるところを訪ねた。それすらも決めてない旅だった。親切な駅長さんが、近くのペンションを紹介してくれた。しかし、どうやら宿と連絡がつかない。まだ携帯電話なんてない時代だ。
「そういえば(ペンションの)奥さんが(たぶん)生協で買い物してたの見たぞ。今日はカレーライスだと思う」という笑い声が駅舎に響いた。
「馬、見に来たんだべ。見ておいで。その間に連絡とっておくから」という言葉を頼りに、徒歩で目的地に向かった。
最初にたどり着いたのは日高軽種馬農協門別種馬場。大好きだったホウヨウボーイが、たった1年だけ過ごした種馬場だ。そのとき、すでにホウヨウボーイはいなかったが、グリーングラスがいた。現役時代の記憶はほとんどないが、美しい響きのある名前は印象的だ。
「あの馬は、人がくると尻をむけるから写真を撮るのは難しいよ」とスタッフに言われ、カメラを片手に放牧地に。
何のことはない。見知らぬ人間に気がついたグリーングラスは、トコトコと近くにやってきた。 初めて間近にみる馬の大きさと、黒光りする迫力ある馬体に圧倒されながらも、夢中でシャッターを切った。
満足そうにする私に「ほかの馬はよいのかい?」と作業を終えたスタッフが声をかけてきた。「えっと、あとは何がいるんでしたっけ」と私。
それまで、好意に満ちていたスタッフの凍った表情は今でも忘れられない。「タネウマ持ちは、業界の花形」という言葉は、相当あとで知ったフレーズだが、競走馬と、それに携わる人たちのプライドを思い知らされた瞬間だった。
その日からスタートした約1週間の馬産地紀行は、新冠、静内、三石を経て、浦河町まで。
シンザンとタケホープ、そしてトウショウボーイが最後の被写体だったと記憶しているが、36枚撮りフィルム20本をすべて撮りきって終えた。まだ車の免許も持たないときだったので、移動は徒歩、それにタクシーとバスを使った。そして、多くの牧場の人たちの好意に甘えさせてもらった。
今考えれば恐ろしいことだが、すべての訪問がアポなしだった。歩いていたら陽がすっかりと落ち、真っ暗になった牧場の門を叩いたこともある。まるで「田舎に泊まろう」の世界だ。
その牧場では本当に「泊まっていけ」といわれて一宿二飯の恩義を受けた。朝食でいただいたおにぎりと味噌汁の味はいまでも忘れることはできない。
すっかり日高の虜になった「東京から、馬の写真を撮りにきた変わり者」はそれから4年間、同じような時期に馬産地日高をたずね、そして今ではほぼ毎週のように日高のどこかにいる。
風景は、すっかり変わってしまったが、今でも変わらない空気と時間が流れている。そんな日高が大好きだ。